大国


アメリカは世界最大の経済大国であり、最も裕福な国の一つです。他の多くの国々と比べて、アメリカは気候緊急事態の影響に対して脆弱ではなく、その影響に対処するのに有利な立場にあります。しかし、アメリカ国内の低所得者、有色人種、先住民地域社会は資源へのアクセスや回復力対策が限られているため、しばしば偏ったリスクに直面しています。アメリカは資源を獲得し、国際貿易を通じて金銭的余剰を生み出すために、多数派世界と生態学的に不平等な取引交換を行っています。
アメリカは地政学的に大きな影響力を持っており、2021年にパリ協定に再加盟し、気候問題への取り組みを改めて強調しました。長い歴史にわたって、アメリカは他のどの国よりも多くの温室効果ガスを排出してきました。現在、アメリカは2番目に多くの温室効果ガスを排出しています。1人当たりの排出量は、世界平均の約3倍です。アメリカでは運輸部門が温室効果ガス排出の最大の原因となっており、エネルギー部門と産業部門がそれに続いています(EPA、2023年)。
気候緊急事態の影響に対処するため、2021年にアメリカで初の国家気候タスクフォースが設立され、極端な気温から住宅を守り、洪水リスク軽減基準を設定し、グリーンジョブを促進し、クリーンエネルギープロジェクトを加速する上で国を支援しています。
参考:
Rankings // Notre Dame Global Adaptation Initiative (University of Notre Dame)
Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad (The White House)
📄Global patterns of ecologically unequal exchange: Implications for sustainability in the 21st century by Christian Dorninger, Alf Hornborg, David J. Abson, Henrik von Wehrden, Anke Schaffartzik, Stefan Giljum, John-Oliver Engler, Robert L. Feller, Klaus Hubacek, Hanspeter Wieland
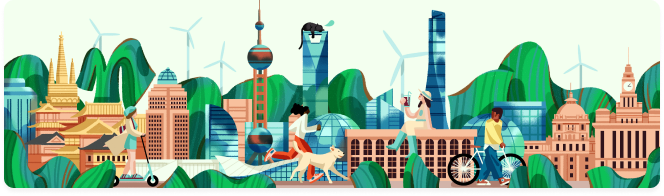
中国は世界で2番目の経済大国で、国際貿易と商業において中心的な役割を果たしています。この国は洪水、熱帯低気圧やそれらに関連する高い危険にさらされています。概して干ばつの影響は少ないものの、中国は最近数十年にわたって最も致命的な熱波に直面しています。地域社会の脆弱性は、その場所や資源へ利用可能性によって異なります。
長い歴史にわたって、中国は世界で2番目に多くの温室効果ガスを排出してきました。現在、中国は世界最大の温室効果ガス排出国です。1人当たりの排出量は、ほぼ世界平均です。中国は“世界の工場”として知られていますが、その工業製造部門は主要な汚染源であり、製造される製品の多くは西側諸国の需要を満たすために作られていることは注目に値します。鉄鋼、セメント、化学薬品、石油化学製品などの産業は、温室効果ガスを含むさまざまな汚染物質排出の原因となっています。
中国は国家が管理している資源を気候危機に向けることに関して高い柔軟性を持ち、回復力を高めています。中国はエネルギー革命を推進し、地球規模の気候管理に取り組むことを約束しています。中国は世界最大の石炭消費国ですが、世界最大のクリーン技術輸出国としても群を抜いています。また、炭素市場を確立して排出量を削減するために、地域的な炭素取引制度を試験的に導入しています。
参考:
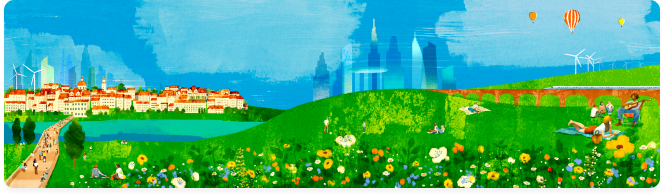
ヨーロッパは世界で3番目の経済圏です。多様性に富み、国によって経済的な豊かさや発展に大きなばらつきがあります。ドイツ、イギリス、フランスなどの国は生活水準が非常に高く豊かですが、ルーマニア、ブルガリア、ギリシャなどの国の貧困率は高くなっています。その結果、気候緊急事態の影響はさまざまで、多くの地域社会(特に低所得層や競争から取り残されたグループ)は依然として非常に脆弱です。
ヨーロッパは群を抜いて多くの開発援助を世界中に提供しています。しかし同時に、アメリカと同様に、ヨーロッパの高所得国は世界の大多数である貧困地域との不平等な取引関係を通じて経済成長を維持し、富と資源を搾取しています。
ヨーロッパは気温の上昇、熱波の頻発、洪水や嵐などの異常気象、降水パターンの変化、氷河の融解、海面上昇など、気候緊急事態の影響を経験しています。これらの変化は大陸全体の生態系、農業、水資源、人間の健康、経済基盤に大きな課題をもたらします。
長い歴史にわたって、ヨーロッパはアメリカと同等の温室効果ガスを排出してきました。現在、ヨーロッパは世界第3位の温室効果ガスを排出しています。1人当たりの排出量は、ほぼ世界平均です。ヨーロッパが気候変動対策のために取った画期的な措置は、2050年までにヨーロッパを気候中立にするための包括的な政策枠組みである欧州グリーンディールです。
参考:
Climate change impacts, risks and adaptation (EU Commission)
A European Green Deal (EU Commission)
📄 Global patterns of ecologically unequal exchange: Implications for sustainability in the 21st century by Christian Dorninger, Alf Hornborg, David J. Abson, Henrik von Wehrden, Anke Schaffartzik, Stefan Giljum, John-Oliver Engler, Robert L. Feller, Klaus Hubacek, Hanspeter Wieland

多数派世界とは“グローバルサウス”または発展途上国の別名です。この呼称は、人類の大半がアフリカ、アジア、中南米、カリブ海、オセアニアの国々で暮らしているという事実を強調しています。
長年にわたり、世界の温室効果ガス排出、資源、経済的富のほとんどはアメリカ、ヨーロッパ、中国によって蓄積されてきました。さまざまなやり方で、これらの国々は他の多くの国々に対する植民地的抑圧の原因となっており、他の地域の発展と気候緊急事態への適応能力に影響を与えています。このため、私たちはこれらの3つの地域をそれぞれ個別のプレイヤーとし、それぞれが気候緊急事態の責任を負うことにしました。多数派世界の国々はそれぞれ異なる特徴、動機、優先事項を持っていますが、歴史的に抑圧されて気候緊急事態の影響を最も受けている地域であることを表すために、私たちはこれらの国々を「eミッション」における1人の“プレイヤー”としました。しかし、気候危機の発生に関してこれらの国々が果たした役割は極めて小さなものです。世界の人口の3分の2を占めているにもかかわらず、多数派世界が排出している温室効果ガスは世界の3分の1に過ぎません。また、1人あたりの排出量は世界平均の約半分です。
異常気象、水不足、農業の混乱、海面上昇、生物多様性の喪失、健康被害、強制退去、適応のための限られた資源は、多数派世界の地域社会に偏った影響を与えています。これらの影響は経済的課題と社会的不平等を悪化させます。
これに対処するために、多数派世界の国々は早期警報システム(ACMAD)の開発、災害への備えの改善(ADPC)、クリーンエネルギー市場の確立(REEEP)のための地域パートナーシップを構築しました。カリブ海青少年環境ネットワーク(CYEN)などの若者の取り組みも、多数派世界でますます人気が高まり、効果を上げています。これらの取り組みは、多数派世界の気候プロジェクトやプログラムを支援する緑の気候基金などの世界的な財政機構によって補完されています。多数派世界の多くの人々は、何世紀にもわたる採掘によって気候危機に対してより脆弱になったことを補うための資金を求めて奮闘し続けています。これは「損失と損害」基金や気候賠償金の形をとることがあります。これらはその後、気候回復性と、よりクリーンな方法での開発のために使われます。
参考: